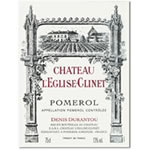帰国した私は、玉手箱を開けた浦島太郎の気分になりました。
住む空間の面積は半減し、当然、お手伝いさんはおらず、 物価は高く、夫はほとんど家におらず、 小さい子供を抱えて近所の公園とスーパーを巡る日々…
同級生や同期達は、着実にキャリアを積み上げているのに、 「仕事をしている」自分がない、つまり収入のない自分が惨めでした。
空気が乾燥し、気候もよかった欧州に比べると、 日本の夏の蒸し暑さは堪え難く、 何度か熱中症になりかかり、 おさまっていたアトピーも再発しました。
そんな中、私は視点を変える方法を見い出せず、 ゆるやかに心を病んでいきました。
このままご飯を作って、洗濯をして、掃除をしての繰り返し。 そしていずれまた、夫の赴任地へと行き、 そこで一から生活を築き、数年したら帰国し… 将来の展望が持てなくなってしまいました。 自分の立ち位置どころか、地図も見失ってしまったのです。
私は誰の話も聞かなくなってゆき、 あらゆる周囲と対立… 「自分、自分」と主張ばかりし、 あらゆる言い訳を正当化しました。 夫と離婚することが、自分の前進になるという突拍子もない勘違いも始まりました。
「うつ病じゃない?」という知人の勧めで心療内科に行き、 診察もカウンセリングも受けましたが、 「正しいこと」が何なのか分かりませんでした。
そうこうしているうちに2年が過ぎ、 私は「一人でも子供を育てて生きていける」という根拠のない自信を頼りに、 私の病の癒えるのを根気よく待っていてくれた夫を振り切り、 両親の反対も押し切って、 小さな子供を連れて家を出たのです。 自分ではうつ病は克服したし、 「自分で選んだ」気持ちになっていましたが、 明らかに私の判断力は病んでいました。
1年間の母子家庭でのアパート暮らしの後、私は再婚しました。 熟慮の上のはずでした。 しかし、「考える」自分の根幹が病んでいる状態での思考、判断は健全ではありません。 再婚相手の言葉、態度のDVが明らかになるのに、1年はかかりませんでした。 それでも、私は後戻りできないと思い込み、なんとか頑張ろうとしました。 自分さえ頑張れば、きっと相手も変わる、事態は良くなると思って…
薄氷を踏むような日々の中、私は自分自身の再構築を始めました。 まずは親に非礼を謝り、とにかく話を聞いてもらいました。 また、親の話も聞きました。 そして、ごく親しい、私を冷静に見てくれながらも励ましてくれる友人に 心を開いて相談しました。 方々にお願いをして、翻訳の仕事を再開しました。 起業塾にも行きました。
数ヶ月先、1年先などわかりませんでした。 ただ、その日、その時をもがきながら懸命に生き抜く、という日々。 自分の不甲斐なさに何度声を上げて泣いたことか、わかりません。
しかし、私は生きていかなければならない。 子供をちゃんと育てなければならない。
チャンスは思わぬところから舞い込みました。
とあるスピリチュアルな講座を日本で開催するアメリカ人から、 テキストや著書の翻訳、さらにワークショップでの通訳を依頼されたのです。 そのタイミングとほとんど平行して、通っていた起業塾の講師がコーチングの講座を開設するにあたり、 アシスタントを募集していたので応募すると採用され、お手伝いをしながらコーチングを学べることになったのです。
この頃から、「本当の自分とは?」をスピリチュアルな観点から考え、 「今をいかに生きるか?」をコーチングの観点から体得していくことができるようになり、 私の人生に光が差してきました。
しかし、現実では夫の物理的な暴力が始まりました。 本当に怖い思いをしました。
子供にどれほどの迷惑をかけ、心に傷を与えてしまったかを思うと、今でも涙が出ます。
ところが、これも私がその場を離れるために必然に起こったこととすれば、 意味があったのです。
それほどのことでもなければ、私は決心がつけられなかったと思います。
コーチングの威力を知って思ったのは、うつになった時にもしコーチングを知っていれば、 またはもしコーチをつけていれば、こんなことにはならなかったのではないかということです。 そして、「コーチングの手法をうつ病予防に役立てられるのでは?」と考えた時、 自らの経験を生かし、コーチとして私が社会貢献できる具体的な方法として 「海外赴任する方とその家族に、うつ病にならずに、現地で成功して戴くために、 事前にお話する機会を作れないだろうか?」とひらめいたのです。
そんな時、信頼できる友人の一人に 「あなたは本当にどうなりたいの?」 と聞かれました。
「自由になりたいと思っている」 と私が答えると、
「思っているうちは実現しない。『なる』と宣言すれば現実になる」 と言われました。
私は即座に「私は自由になります」と、 自分自身と宇宙に宣言しました。
すると、即、奇跡は起こりました。 私の思いに賛同してくれる人が現れ、会社を一緒に起こすことになったのです。 それが、コーチ仲間であった現D-Lifeの社長です。 同時に、経済的自立のめどが立ったので 「再婚したのだから離婚してはならない」という思い込みから解き放たれ、 私は生きる場所を自ら選んで移りました。
自由になろうとあくせく努力するのではなく、思いの強さに現実がついていく感覚で、 たしかに物理的な大変さはあっても、自然な意味でのあるべき姿を感じられました。


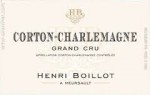 ・産地 :フランス ブルゴーニュ地方 アロース・コルトン
・産地 :フランス ブルゴーニュ地方 アロース・コルトン